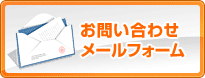法人や会社を設立してから順調に売上が伸び、一定の要件を満たすと課税事業者となり消費税の支払義務が生じます。
実際に負担しているものではなく消費者から預かっていた消費税額を支払っているのですが、まとめてドンとくるとやはり負担に感じる方が多いかと思います。
消費税額の計算例
通常の消費税額の計算は、課税資産の譲渡等を合計した金額から消費税額を求めることになります。
例えば、
税抜価格 93円
消費税(8%) 7円
税込価格 100円
のレシートが100枚ある場合全ての取引を合計し、その合計額から消費税額を求めます。
合計売上高 100円× 100枚 = 10,000円
消費税額 10,000円× 8%÷108% = 740円
となり、消費税額として740円を納付することになります。
ただ、実際に消費者から預かっている消費税額はレシート毎に記載されている消費税額7円×100枚=700円となります。
この場合には、実際に預かっている消費税額700円と納税額740円の差額40円を企業が負担して支払っていることになります。
そもそも消費税とは企業が負担するものではなく、消費者が負担するものですので、消費者から実際に預かっている金額で消費税額を計算する方法が特例として認められています。
事項では、その特例についてみていきます。
課税標準額に対する消費税額の計算の特例とは
この規定は、「課税標準額に対する消費税額の計算の特例」(以下、「旧規則第22条第1項の規定」といいます。)とされ、「税抜価格」を前提に、決済段階で上乗せされる消費税相当額の1円未満の端数処理に伴う事業者の負担等に配慮して、少額・大量の取引を行う小売業者等を念頭に設けられていた特例制度です。
簡単に説明すると、前述したように個々の取引ごとのレシート等に明示された消費税額を直接合計して消費税額を求めることができるものです。
ただし、皆さんご存知の通り「税込価格」の表示を行う総額表示が義務付けられたことで、「税抜価格」を前提としたこの旧規則第22条第1項は廃止されました。(平成16年4月1日)
※旧規則第22条第1項は、課税事業者が、課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を、その課税資産の譲渡等の対価の額(本体価格)とその課税資産の譲渡等に課されるべき消費税等相当額とに区分して領収する場合に、その消費税等相当額の1円未満の端数を処理している時にはその端数を処理した後の消費税等相当額の課税期間中の合計額を基礎として、その課税期間の課税標準額に対する消費税額とすることができるというものです。
廃止はされましたが、当分の間経過措置が設けられています。
事項ではその経過措置について見ていきます。
経過措置の概要
経過措置は、取引の形態等によって下記の3つに分類されています。
1.「税抜価格」を前提とした代金決済を行っている場合
総額表示義務の規定の適用を受けない課税資産の譲渡等(事業者間取引等)については、代金の決済に当たって、取引の相手方へ交付する領収書等で、その取引における「課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格)の合計額」と「その税抜価格の合計額に税率を乗じて1円未満の端数を処理した後の消費税及び地方消費税の合計額(以下「消費税等相当額」といいます。)」を区分して明示している場合には、当分の間、旧規則第22条第1項の規定を適用することができます。
2.「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合
課税資産の譲渡等(総額表示義務の規定の適用を受けない事業者間取引等も含まれます。)について、決済上受領すべき金額(例えば、複数の商品を一括して販売し、その代金を一括して受領する場合には、一括販売した商品の税込価格の合計額)に含まれる「消費税等相当額
(その決済上受領すべき金額に「(100+税率)分の税率」を乗じて算出した金額)」の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に明示した場合には、当分の間、その端数を処理した後の消費税等相当額を基礎として課税標準額に対する消費税額を計算することができます。
上記2は、商品単品ごとに消費税等相当額の端数処理を行っている場合には適用できません。
3.総額表示を行っているが「税抜価格」を基に計算を行う場合
総額表示義務の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等(対消費者取引)については、総額表示を行っている場合で、「税抜価格」を基に計算するレジシステム等を使用せざるを得ない場合等のやむを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合には、 平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について、当分の間、旧規則第22条第1項の規定を適用することができます。
消費税転嫁対策特別措置法第10条第1項≪総額表示義務に関する消費税法の特例≫の規定の適用を受ける場合にも、総額表示を行っているものとして経過措置が適用されます。
上記3は、平成19年3月31日までに行われる課税資産の譲渡等に適用されることとされていたものが改正され、平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について当分の間適用されます。
上記の各経過措置を適用するためには、それぞれの経過措置に定める方法により1円未満の端数処理を行った後の消費税等相当額とその基礎となった税込価格又は税抜価格を領収書又は請求書等において明示していることが必要です。
したがって上記2の経過措置を適用するためには、一括販売した複数の商品の「税込価格」の合計額と、この合計額に「(100+税率)分の税率」を乗じて算出された消費税等相当額の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に明示していることが必要です。
また、上記1又は3を適用するためには、一括販売した複数の商品の「税抜価格」の合計額と、この合計額に税率を乗じて算出された消費税等相当額の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に区分して明示していることが必要です。
コンビニやスーパーマーケット等を経営されている方で少額・大量の取引を行っている方は、この特例を適用した方が消費税額の負担が軽くなるかと思います。
領収書の記載要件等がありますので、詳しい取扱いや適用にあたっては事前に税理士へご相談されることをお勧めいたします。
消費税の簡易課税方式を選択する際の注意点
先にもお伝えしましたが簡易課税方式を選択するには、納税地を所轄する税務署長にその選択したい課税期間開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、原則として、2年間は原則課税方式に変更することはできません。
もしも簡易課税方式を選択した後、設備投資等で大きな金額の買い物をした場合、実際に支払った消費税がいくら大きくても消費税の計算上差引くことができないので注意が必要です。
簡易課税制度の適用をとりやめて原則課税方式に変更したい場合は簡易課税方式をやめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用ができません。
消費税の課税方式の基本的な有利不利判定
簡易課税方式の方が計算が簡単そうだし、実際に支払いがなくてもみなし金額で預かった消費税から引き算ができて、なんとなく有利な感じがします。
原則課税方式と簡易課税方式、それぞれどのような場合に有利となるのでしょうか。
例1
原価率が40%の製造業を営む会社の場合です。
課税売上2,000万円(税抜:預かった消費税160万円)
売上原価に係る課税仕入800万円(税抜:支払った消費税64万円)
販管費に係る課税仕入400万円(税抜:支払った消費税32万円)
「原則課税方式」と「簡易課税方式」のどちらを選択した方が有利でしょうか。
※ここでは国税と地方税を分けず、消費税率8%で計算します。
<原則課税方式の場合>
預かった消費税160万円-支払った消費税(64万円+32万円=96万円)=消費税納税額64万円となります。
<簡易課税方式の場合>
製造業の事業区分は第三種事業で、みなし仕入率は70%です。
仕入控除税額は160万円×70%=112万円です。
預かった消費税160万円-仕入控除税額112万円=消費税納税額48万円となります。
この場合簡易課税方式を選択していた方が有利となります。
同じ事業を行っていても、計算方式の選択次第で納税額に64万円と48万円で16万円の差が生まれました。
それでは次の場合はどうでしょうか。
例2
例1と同じ原価率が40%の製造業を営む会社ですが、業績悪化で売上が下がるとどうなるでしょうか。
課税売上1,000万円(税抜:預かった消費税80万円)
売上原価に係る課税仕入400万円(税抜:支払った消費税32万円)
販管費に係る課税仕入400万円(税抜:支払った消費税32万円)
<原則課税方式の場合>
預かった消費税80万円-支払った消費税(32万円+32万円=64万円)=消費税納税額16万円となります。
<簡易課税方式の場合>
製造業の事業区分は第三種事業で、みなし仕入率は70%です。
仕入控除税額は80万円×70%=56万円です。
預かった消費税80万円-仕入控除税額56万円=消費税納税額24万円となります。
売上が減少すると売上原価も減少しますが、販管費はあまり変わらないものと仮定しました。
売上が減少すると販管費部分の支払った消費税の割合が大きくなります。
16万円と24万円で8万円ほど原則課税方式を選択しておいた方が有利となりました。
今回挙げた例は条件をかなり簡略化したものです。
貴社の実際の状況に応じて考える必要があります。
消費税の計算方式
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以上の事業者は、納税の義務が発生します。
この免税事業者となるか課税事業者となるかを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として1年相当に換算した金額により判定することとされています。
具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税込の金額で判定します。
新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人に該当する場合は、納税義務は免除されません。
課税事業者となった場合、消費税の計算方法には「原則課税方式」と「簡易課税方式」という2つの方式があります。
「原則課税方式」は、課税売上に係る消費税額(預かった消費税)から課税仕入に係る消費税額(支払った消費税)を差引いて計算します。
基本的にはこちらの方式で消費税額を計算します。
「簡易課税方式」は、課税売上に係る消費税額(預かった消費税)から実際の課税仕入に係る消費税額(支払った消費税)を差引いて計算するのではなく、預かった消費税額に一定の率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を支払った消費税として簡便的に納税額を計算する方式です。
売上の種類によって日本標準産業分類を基に卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
みなし仕入率は下記の通りです。
・第一種事業(卸売業) 90%
・第二種事業(小売業) 80%
・第三種事業(製造業等) 70%
・第四種事業(その他の事業) 60%
・第五種事業(サービス業等) 50%
・第六種事業(不動産業) 40%
その課税期間の前々年又は前々事業年度「基準期間」の課税売上が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出していることを条件に、簡易課税制度の適用を受けることができます。